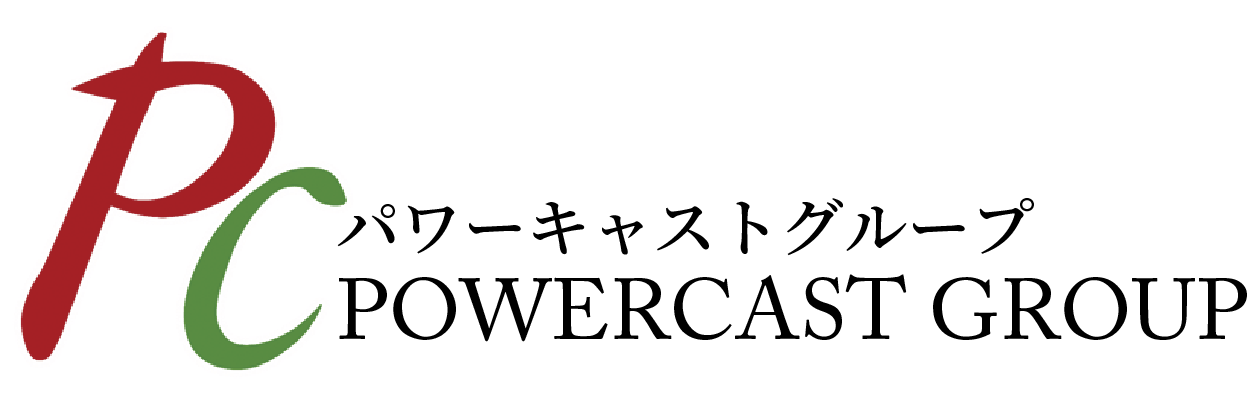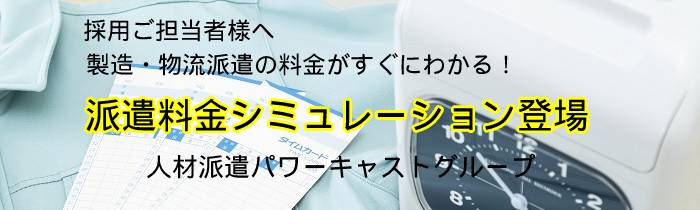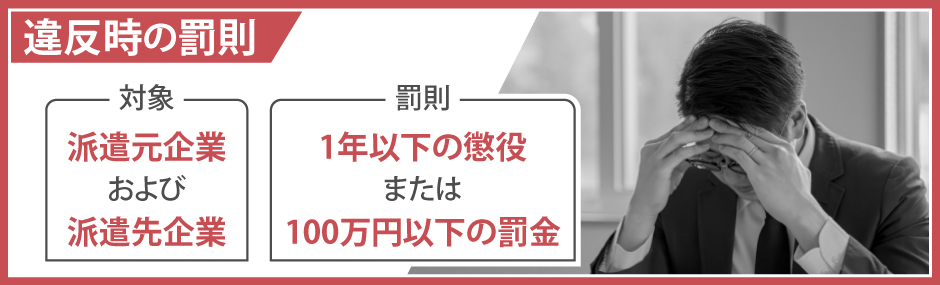派遣禁止業務とは?禁止されている理由と例外について徹底解説
派遣労働は、企業が必要なときに人材を活用できる便利な制度です。ただし、労働者派遣法は、派遣労働者を使うと違法になる、「派遣禁止業務」を定めています。派遣元企業や派遣先企業の双方が法律を守り、適切に派遣労働者を活用するためにも、派遣禁止業務とは何か理解しておくのが大切です。
この記事では、派遣禁止業務とは何か、派遣禁止業務が整備された背景、および禁止されている具体的な業務内容について分かりやすく解説します。禁止の例外となる業務や、違反した場合の罰則についても紹介するので、派遣労働にかかわる方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 派遣禁止業務とは?
派遣禁止業務とは、労働者派遣法で定められた「派遣労働者が行ってはならない業務」のことです。法律用語では「適用除外業務」と呼ばれます。
職業ではなく業務単位で禁止されているため、派遣禁止業務にかかわる職業であっても、業務そのものを行わなければ法律違反になりません。例えば、弁護士などの士業は派遣禁止業務にあたりますが、弁護士事務所の経理作業を行うことは許容されます。
派遣禁止業務を行わせた場合、たとえ知らなかったとしても派遣先企業と派遣会社の双方に罰則が科されます。
1-1. 人材派遣の仕組み
人材派遣とは、人材派遣会社(派遣元)が労働者を自社で雇用し、その労働者をほかの企業(派遣先)に派遣して働かせる仕組みです。労働者は派遣元企業と雇用関係にあり、給与の支払いや雇用契約の管理は派遣元企業が行います。一方、日常の業務内容や職場での指示・命令は派遣先企業が担当します。
派遣労働では、雇用主である派遣元企業と実際の勤務先である派遣先企業が異なるため、業務内容に関するトラブルが起こりやすい点に注意が必要です。派遣先企業での労働条件が派遣契約時の説明と異なるといった問題が起きた場合、派遣禁止業務に抵触する可能性が高まります。したがって、派遣元・派遣先企業の双方が労働条件を明確にするのが大切です。
1-2. 派遣禁止業務が整備された理由
労働者派遣法は1999年に法改正された際に、許可された業務のみ派遣を許容するポジティブリスト方式から、派遣禁止業務を定めるネガティブリスト形式になりました。理由として、改正前は基本的に26業種の専門性が高い業務につく場合は派遣労働が許容されていましたが、以降は業務が原則自由化された点にあります。
派遣労働者を受け入れるメリットよりデメリットのほうが大きいと考えられる以下のような業務は、規制緩和後も派遣禁止業務に選ばれています。
- 職務内容の専門性が高い
- 業務内容が多くの人の生命を左右する
- 独自の制度や権限があり、派遣制度にそぐわない
例えば、医療や建築関係の業務は、専門性が高いだけでなく人間の命にかかわる重要な仕事のため、原則として派遣労働者は行えません。ほかにも、指揮命令系統が混乱する恐れのある警備業や、独自の雇用調整制を持つ港湾運送業は派遣制度の考え方に合わないことから、派遣労働者が業務をするのは不適切です。
2. 派遣が禁止されている業務内容一覧と例外
派遣社員が行うのが禁止されているのは、大きく分けて5つの業務です。ただし、一部の業務においては例外があり、派遣が許容されるケースがあります。それぞれの業務の禁止理由や、禁止されている業務内容の詳細について解説します。
2-1. 港湾運送業務
港湾運送業務は、港湾において貨物の積み下ろしや運搬、船内での荷役作業などを行う業務です。禁止されている業務の例は、以下の通りです。
- 船舶への貨物の積み込みや荷降ろし
- 船内や港湾施設での貨物の位置調整、固定作業
- 貨物の梱包、解体、包装修理
- 貨物の積み下ろし場所の清掃、整備
- 港湾内での貨物の運搬、倉庫への搬入出
など
港湾運送業務は、気象条件や船舶の入出港により労働需要が大きく変動し、労働者の雇用が不安定になりやすい特殊な業界です。そのため、労働者の雇用安定を図る目的で、労働者派遣法とは別に「港湾労働法」に基づく労働力需給調整制度が設けられています。派遣労働を導入すると、制度の機能が損なわれる可能性があることから、法律で派遣が禁止されています。
ただし、例外として事務所内での事務業務や、荷役に使う機器のメンテナンスなどの業務は派遣が許容されています。また、港湾労働者派遣制度が適用される東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門の6大港では、港湾労働者雇用安定センターを通じた人材派遣が可能です。
2-2. 建設業務
建設業務とは、土木・建築・その他工作物の建設、改造、修理、解体などの作業、および準備に関する業務のことです。禁止されている業務の例は、以下の通りです。
- 建設現場での資材の運搬、組み立て、解体作業などの建設作業全般
- 掘削、埋め立て、地盤改良などの土木作業全般
- 電気工事、配管工事、空調設備など設備工事作業全般
- 塗装、内装、外装の仕上げや補修作業
- 建設現場での清掃、資材や機材の整理整頓
など
建設業務は高所作業や重機の操作など危険を伴う作業が多く、安全管理が難しいほか、多重下請け構造が発生しやすい課題を抱えています。加えて、工事の品質が低下すると、人命が失われ、巨額の経済的損失が生まれる巨大事故につながる恐れもあります。そのため、責任の所在が不明瞭になりかねない派遣労働は一律で禁じられている状況です。
例外として、事務所での一般的な事務・経理業務、設計など現場外の技術業務、および条件を満たしていれば施工管理業務は派遣労働者が行っても問題ありません。
2-3. 警備業務
警備業務とは、施設や人々の安全を守るための業務を指します。禁止されている業務の例は、以下の通りです。
- 建物や施設内の巡回、監視、異常の発見・対応
- イベント会場や商業施設での人や車両の誘導、混雑緩和
- 現金や貴重品輸送にあたっての護衛や監視
- 身辺警護や付き添い
- 防犯カメラの監視、セキュリティシステムの操作
など
警備業務は「警備業法」により、警備員が直接雇用され、警備会社の指揮命令下で業務を行うように義務付けられています。雇用先と派遣先企業が違う場合、教育や指揮命令系統が曖昧になり、緊急時の対応や責任の所在が不明確になるため、派遣労働者の雇用は一切認められていません。
2-4. 病院・診療所などにおける医療関連業務
医療関連業務とは、医師や看護師、薬剤師などの医療従事者が行う専門的な業務のことです。禁止されている業務の例は、以下の通りです。
- 医師による医業全般
- 歯科医師による歯科医業
- 薬剤師による調剤業務
- 看護師による療養上の世話、診療の補助
- 保健師による保健指導
など
患者の生命や健康を守る医療業務においては、高度な専門知識とチームワークが欠かせません。しかし、短期雇用が前提となる派遣労働者がチームに加わった場合、連携に問題が発生します。また、派遣会社側と派遣先の医療機関で教育内容が異なる場合、患者が望んだ医療を受けられなくなる恐れもあります。したがって、医療機関では派遣労働が原則禁止です。
ただし、派遣期間終了後に直接雇用を前提としている場合、および産休・育休・介護休業を取得した労働者の代替をする場合は派遣が許可されています。また、へき地などの医師不足が深刻な地域では、厚生労働省の認可のもと一定条件下で派遣が可能です。
2-5. 弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業務
「士」業務とは、国家資格を持つ専門家が行う業務を指します。禁止されている業務の例は、以下の通りです。
- 弁護士
- 税理士
- 公認会計
- 司法書士
- 行政書士
- 弁理士
などの業務全般
士業には高度な専門性と独立性が求められ、依頼者の利益を最大限守る形で直接雇用を受けて業務を遂行する必要があります。しかし、派遣労働の場合、派遣された士業者は業務上派遣会社に自身が得た秘密を明かさざるを得ない可能性を否めません。業務の独立性や守秘義務が損なわれるほか、責任の所在も不明瞭になることから、派遣労働は原則として禁止です。
ただし、士業の専門家を補助する目的で事務作業やアシスタント業務を行う範囲であれば、派遣労働が認められます。また、公認会計士・税理士などの場合、監査や税務といった独占業務にあたらない業務であれば、一部派遣が認められている場合があります。
ほかにも、業務自体は派遣禁止業務にあたらない場合でも、以下のような業務を派遣労働者は行えません。
- ストライキや労働争議が起きている事業所での業務
- わいせつ行為を伴うなどの公衆衛生・公衆道徳上有害な業務
3. 派遣禁止業務違反時の罰則について
派遣禁止業務に派遣労働者を従事させた場合、派遣元企業と派遣先企業の双方に対して「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。また、たとえ違法行為が軽微と判断された場合でも、厚生労働省からの指導・助言がなされ、場合によっては社名が公表されます。信用失墜や取引先への影響といった間接的なリスクも伴うので、派遣禁止業務を派遣社員に行わせないようにしましょう。
さらに、違法派遣を行った派遣先企業を、派遣労働者に対して労働契約の申し込みをしたとみなす「労働契約申込みみなし制度」が適用される可能性があります。適用された場合、派遣労働者が承諾すれば、派遣先企業はその労働者を直接雇用しなくてはなりません。
なお、派遣労働者が違反を厚生労働大臣に申告した場合、派遣元・派遣先企業がその労働者に不利益な扱いをするのは禁止されています。違反した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科され、派遣元企業は事業許可の取消しや事業停止命令の対象となる可能性もあります。
まとめ
派遣労働が禁止されているのは、人命にかかわる・専門性が高い業務、あるいは制度上派遣労働が合わない業務です。また、ストライキが起きている事業所への派遣や、公衆衛生・公衆道徳上有害な業務については、派遣禁止業務でない場合でも禁止されています。
労働者派遣法に違反すると、企業には罰金や懲役といった厳しい罰則が科されるだけでなく、社会的な信用を失う大きなリスクもあります。ただし、派遣禁止業務を行う職種であるからといって、必ずしも派遣受け入れができないわけではなく、またいくつか例外が認められている点は覚えておきましょう。