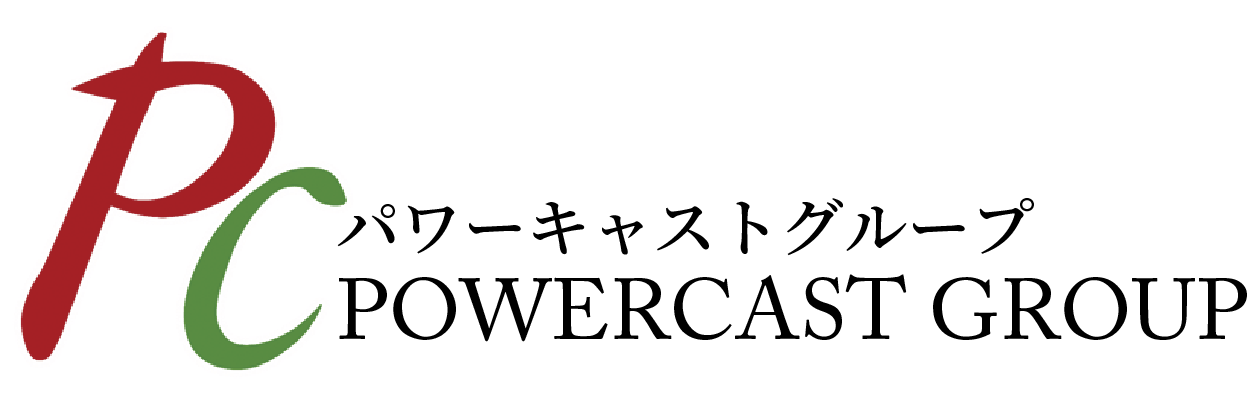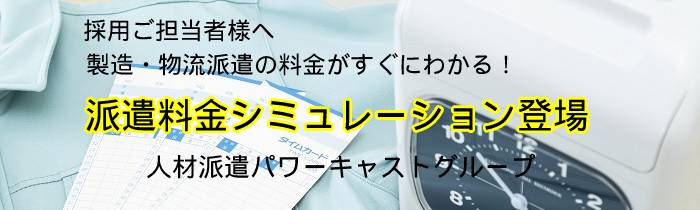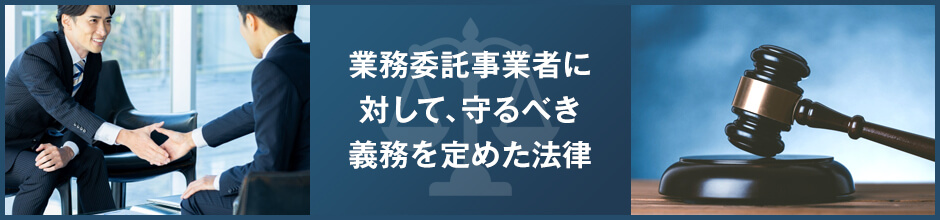フリーランス新法とは?分かりやすく対象者・規制内容を解説
働き方の多様化に伴い、ギグワーカーやクラウドワーカーなど、フリーランスで働く方も増加しています。一方で、フリーランスは組織に守られていないため立場が弱く、買いたたきや口約束に基づくあいまいな取引などがしばしば発生していました。そこで、国はフリーランスを保護し、適正な取引をするためにいわゆる「フリーランス新法」を2024年11月に制定しました。
この記事では、フリーランス新法とは何か、対象者や制定の背景、規制内容について分かりやすく解説します。フリーランスの雇用を考えている事業者の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
目次
1.フリーランス新法とは?
フリーランス新法とは、主にフリーランスに仕事を依頼する事業者に対して、業務委託の厳守事項を定めた法律です。報酬の支払期日の設定や、取引条件の明示などを義務付けるものとなっています。
フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス保護新法」と呼ばれることもあります。フリーランス新法は以下のことを目的とした法律です。
- フリーランス・発注事業者間の取引の適正化
- フリーランスの就業環境の整備
フリーランス新法は2024年11月1日に施行され、以降のフリーランスと事業者の取引がすべて対象となっています。
もしフリーランス新法に違反すると、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働大臣から指導や立ち入り検査を受け、拒否した場合は50万円以下の罰金が科されるケースがあります。健全な事業運営のためにも、企業はフリーランス新法について知っておくことが大切です。
1-1.フリーランス新法の対象者
フリーランス新法の対象となるのは、従業員を使用しない業務委託の相手方である事業者になります。
一般的なフリーランスの中には従業員を雇用している人もいるものの、フリーランス新法においては個人で働くフリーランスのみが該当します。ただし、従業員の雇用が短期間もしくは一時的な場合はフリーランスとみなされるため注意が必要です。
また、フリーランス新法の対象者に業種や業界、年齢の制限はありません。以下のような人は、すべてフリーランス新法の対象になります。
- 企業に属さず個人で働く方
- 従業員のいない法人(いわゆる一人社長)
- 従業員を雇っていない建築・建設現場の職人(いわゆる一人親方)
- 定年を迎えた元従業員への業務委託
一方、フリーランス新法における発注事業者とは、従業員を雇用している法人や個人事業主を指します。フリーランスと一般消費者との間やフリーランス同士の取引は、「取引条件の明示義務」を除いてフリーランス新法の対象になりません。
2.フリーランス新法が制定された背景
フリーランス新法が制定された背景にあるのが、フリーランス人口の増加です。デジタル社会の進展とともに働き方の多様化が進んだ結果、ギグワーカーやクラウドワーカーなどの新しい働き方が広まり、フリーランス人口が増加しました。現在では、IT関連業界やクリエイティブ分野、エステや飲食サービス、配送、建築など、さまざまな分野・業界でフリーランスが活躍しています。
一方で、フリーランスと発注事業者との間でトラブルが発生するケースも多く聞かれるようになりました。フリーランスは発注者である企業と比較して立場が弱くなりやすく、以下のようなトラブルが生じるケースも少なくありません。
- 進めていた仕事が突然キャンセルになった
- 不当に低い報酬で発注された
- 報酬が期日までに支払われなかった
上記のようなトラブルの原因として、フリーランスは発注事業者と雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶため、労働基準法の対象にならないことが挙げられます。そこで、フリーランスでも安心して働ける環境を整備するために、フリーランス新法が制定されました。
3.フリーランス新法の規制内容を分かりやすく解説
フリーランス新法では、発注側の事業者にさまざまな義務が課せられています。違反した場合、ペナルティを課せられるなどのデメリットが生じる可能性があるため注意が必要です。
以下では、フリーランス新法の主な規制内容を分かりやすく解説します。
3-1.取引条件の明示義務
フリーランスに業務委託をする際、発注事業者は以下のように取引条件を書面などで明示しなければなりません。
- 給付の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 業務委託事業者やフリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査をする場合)検査完了日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
取引条件の明示方法は、書面のほか、電子メールやチャットツール、SNSといった電子的な方法でも認められています。取引条件を明示し、記録に残すことで、言った・言わないを巡る取引上のトラブルを避けられるでしょう。
なお、取引条件の明示義務は、フリーランスと発注事業者間だけでなく、フリーランス同士の取引や一般消費者とフリーランス間の取引でも義務付けられています。
3-2.報酬支払期日の設定および期日内の支払い義務
発注事業者は、成果物の受領日から60日以内に報酬支払期日を設定し、期日内にフリーランスに支払わなければなりません。
■特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第4条
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
引用:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」引用日2025/2/14
例えば、月末締め・翌々月15日払いの場合は支払い日まで最大75日の期間があるため、フリーランス新法の遵守事項に抵触します。締め日から支払い日までが長い企業は、この機会に見直しを行う必要があるでしょう。
フリーランスと発注事業者間の取引では、報酬の支払いに関するトラブルも多く挙げられます。「本当に報酬が支払われるのか」という不安はフリーランスの業務の遂行や生活にも直結するため、報酬支払期日に関する事項が定められています。
3-3.募集情報の的確な表示義務
発注事業者が広告などを使ってフリーランスを募集する場合、最新の情報を的確に表示しなければなりません。募集に際して、虚偽の表示または誤解を与えるような表示をすることは禁止されています。
広告などでの募集内容と実際の取引条件が異なることで、フリーランスが不利益を被ったり、希望に沿った別の業務を受注する機会を失ったりするケースが存在します。発注事業者は、雇用契約を締結する場合と同じように的確な条件を表示することが大切です。
3-4.禁止行為の遵守義務
フリーランスに業務委託を行う発注事業者には、7つの禁止行為に対して遵守義務が定められています。7つの禁止事項の大まかな内容は以下の通りです。
- 成果物を正当な理由なく受領拒否すること
- 報酬を不当に減額すること
- 成果物を正当な理由なく返品すること
- 著しく低い報酬で発注すること
- 発注事業者指定商品の購入・利用を強制すること
- 発注事業者への利益提供要請を行うこと
- 不当に給付内容の変更またはやり直しを要請すること
例えば、一度決めた約束を理由なく撤回したり、受け取った成果物を返品したりする行為は禁止されています。
3-5.中途解除時の事前予告義務
発注事業者がフリーランスに継続して業務委託をしている場合、中途解除をする際には事前予告をしなければなりません。中途解除の事前予告は、原則として中途解除日あるいは契約終了日の少なくとも30日前までに行う必要があります。
■特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第16条
特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
引用:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」引用日2025/2/14
事前予告の方法は、書面や電子メール、ファクシミリなどが想定されます。また、フリーランスが中途解除の理由開示を求めた場合、発注事業者は応じなければなりません。
なお、不正行為や契約違反などの禁止行為が事前に明示され、フリーランス側が合意していた場合は、即日の契約解除が可能なケースもあります。
3-6.育児・介護との両立への配慮義務
発注事業者は、フリーランスに一定期間以上の継続的な業務委託を行う場合、妊娠・出産・育児や介護と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければなりません。
育児・介護との両立への配慮はフリーランスからの申し出に応じる形で行われますが、現時点で「必要な配慮」の具体的な内容は定められていません。そのため、どこまで応じるかの判断は難しいと言えます。しかし、育児・介護と仕事の両立のためにやむなくフリーランスとして働いている人も少なくないため、取引を行う発注事業者にも一定の配慮が求められます。
なお、厚労省は配慮すべき例として以下を挙げています。
① 妊婦健診がある日について、打合せの時間を調整してほしいとの申出に対し、調整した上で特定受託事業者が打合せに参加できるようにすること。
② 妊娠に起因する症状により急に業務に対応できなくなる場合について相談したいとの申出に対し、そのような場合の対応についてあらかじめ取決めをしておくこと。
③ 出産のため一時的に特定業務委託事業者の事業所から離れた地域に居住することとなったため、成果物の納入方法を対面での手渡しから宅配便での郵送に切り替えてほしいとの申出に対し、納入方法を変更すること。
④ 子の急病等により作業時間を予定どおり確保することができなくなったことから、納期を短期間繰り下げることが可能かとの申出に対し、納期を変更すること。
⑤ 特定受託事業者からの介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したいとの申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること。
3-7.ハラスメント対策体制の整備義務
ハラスメント行為によってフリーランスの就業環境が害されることがないよう、発注事業者はハラスメント対策体制の整備を行わなければなりません。具体的には、ハラスメント相談窓口の設置や、外部機関への相談対応の委託、ハラスメント防止に関する研修の実施などが挙げられます。
フリーランスが発注事業者側からハラスメントを受けたという事例は複数存在します。そこで、フリーランスが安心して業務に取り組めるよう、発注事業者側に従業員を雇用するときと同様のハラスメント対策体制の整備が求められることになりました。
まとめ
フリーランス新法には、取引条件や報酬の支払期日、禁止行為などを明確化する形で、業務委託契約を適切に行うルールが定められています。フリーランスとの信頼関係を築き、コンプライアンスを守って適切な発注をするために、フリーランス新法に則った対応は必須です。
従来の運用と異なる対応が求められるケースもあるので、事業者側はたとえ明白な問題がこれまでなかったとしても、自分たちの対応が適切かチェックする必要があります。フリーランス新法に違反すると公的機関による指導や立ち入り検査を受けるほか、50万円以下の罰金を科せられるケースもあるため、正しい対応ができているかすぐに再確認しましょう。