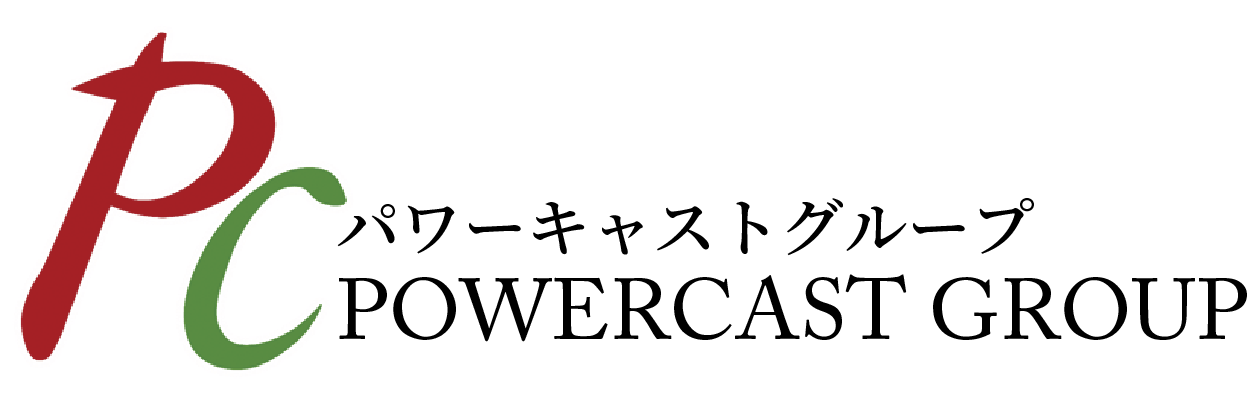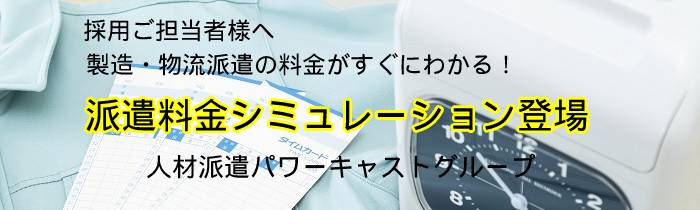ハインリッヒの法則とは?ヒヤリハットが労災事故につながる理由を解説
職場で起こる事故は、突然のように見えて、実は小さな危険の積み重ねによって引き起こされています。「ハインリッヒの法則」では、1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するとされます。事故の未然防止には、このヒヤリハットをいかに捉え、共有し、対策へとつなげるかがカギです。
当記事では、ヒヤリハットがなぜ発生するのか、どのような事例があるのかを具体的に解説し、事故防止につなげる実践的な方法を紹介します。
目次
1.ハインリッヒの法則とは
ハインリッヒの法則とは、労働災害の予防に活用される有名な経験則で、「1:29:300の法則」とも呼ばれます。
アメリカの損害保険会社の技師ハインリッヒが、数千件の労働災害を統計的に分析した結果として1931年に提唱しました。1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故、さらに300件のヒヤリハット(事故には至らなかったが危険を感じた出来事)が潜んでいるという内容です。
ハインリッヒの法則から、重大事故を未然に防ぐためには、日々の小さな異常や不注意に目を向け、早期に改善することが大切だと分かります。この法則は、製造業や建設業、医療・運輸など多くの業種で安全教育の基本として活用されています。
1-1.ハインリッヒの法則とバードの法則の違い
ハインリッヒの法則と似た考え方に「バードの法則」があります。これは1969年、フランク・バード氏が297社・175万件の事故データをもとに提唱したもので、「1:10:30:600の法則」として知られています。
バードの法則では、1件の重大事故の背後に10件の軽傷事故、30件の物損事故、600件の傷害も物損もない事故が存在するとされ、ハインリッヒの法則と違い、物損事故が加わっているのが特徴です。
どちらの法則も、重大事故の背景には数多くの軽微なトラブルや危険な兆候があるという点で共通しています。事故防止のためにはヒヤリハットを見逃さず、情報を共有して早期に対策を講じましょう。
2.職場でヒヤリハットが起きる理由
職場でヒヤリハットが発生する主な要因には、下記が挙げられます。
- 慣れや焦りによる見逃し
- 設備や作業手順の不備
- 疲労による判断力の低下
作業に慣れることで緊張感が薄れたり、納期や時間に追われたりすることは、ヒヤリハットの原因の1つです。さらに、設備や作業手順に不備があると、安全な行動がとれず、危険な状況に直面するリスクも高まります。また、長時間労働や休息不足によって疲労が蓄積すると、注意力や判断力が低下し、小さな異変を見逃してしまうこともあります。
これらの要因が重なることで、事故には至らないまでも、ヒヤリとしたりハッとしたりするような危険な場面が生まれてしまいます。
3.ヒヤリハットの事例
ヒヤリハットは、重大な災害や事故の一歩手前の出来事であり、放置すれば深刻な労災につながる可能性があります。ここでは、実際に報告された事例の中から、「転倒」「墜落・転落」「飛来・落下」「はさまれ・巻き込まれ」の4つの典型例について、具体的な事象とともに解説します。
3-1.転倒
職場でのヒヤリハット事例の中でも、転倒は最も頻繁に報告されているものの1つです。厚生労働省のサイトに掲載されている転倒に関する事例には、以下のようなケースがあります。
- 厨房で熱湯の入った大鍋を運搬中、床が滑って転倒しそうになった
- 雪道で荷物を持って歩行中、足を滑らせて転倒しそうになった
- 清掃中の浴室で濡れた床に足を取られ、転倒しか けた
- 台車作業中にバランスを崩し、転倒しそうになった
- 商品を下ろす際、足元の荷物につまずいて転倒しかけた
これらの事例に共通するのは、「足元の不安定さ」「視界の悪さ」「周囲の環境への配慮不足」です。重い物を持っていると視界が遮られ、床の滑りやすさや障害物に気づかず、バランスを崩しやすくなります。また、床材の性質や気象条件、作業靴の滑り止め性能も影響します。
重い物はなるべく2人以上で運ぶようにし、床の滑りやすさに注意して清掃や点検をこまめに行いましょう。
3-2.墜落・転落
墜落・転落も、作業環境によっては重大事故に直結しかねないヒヤリハットの一種です。厚生労働省の事例には、以下のようなケースが報告されています。
- 脚立での剪定作業中、足を滑らせて落下しそうになった
- 屋上で設備異常を確認中、後退しながら写真を撮っていたところ、縁から転落しかけた
- トラックのテールゲートリフターから降りる際、足を踏み外して落下しそうになった
- 倉庫内でリフトに乗って商品を収集していたところ、バランスを崩した
- ビルの柵越しに道具を渡そうとして、吹き抜け部分に落ちそうになった
これらの事例では、「高所作業時の安全配慮不足」「一時的な判断ミス」が大きなリスクとなっています。特に脚立や屋上、リフトなどは不安定な足場である場合が多く、転落防止措置や正しい作業手順が欠かせません。
防止するには、事前に危険箇所を把握し、必要に応じて墜落制止用器具(安全帯)の装着や、二人一組での作業体制を整えましょう。
3-3.飛来・落下
飛来・落下のヒヤリハットは、特に重量物の取り扱いや高所作業を伴う現場で多く発生しています。厚労省の報告事例には以下のようなものがあります。
- 天井クレーンのワイヤーが切れ、吊り上げていた鋼板が落下した
- 大ハンマーの頭部が抜け、丸太杭のそばにいた作業員にぶつかりそうになった
- 足場解体中、資材が落下し、下の歩行者に当たりそうになった
- トラックからロールボックスパレットが荷卸し中に落下しかけた
- グラインダー作業中、削った鋼板の破片が足元に落ちた
これらの事例に共通するのは、「固定・確認の不十分さ」「作業エリアへの意識の低さ」です。対策としては、使用する器具や部材の事前点検を確実に行い、固定が甘い部分や老朽化した道具は使用しないことが挙げられます。
3-4.はさまれ・巻き込まれ
「はさまれ・巻き込まれ」は、機械の操作や車両の接近などによって生じる危険の一種で、命に関わる深刻な事故に発展する可能性があります。以下は厚労省によって報告された代表的なヒヤリハット事例です。
- プレス機に指を入れたところ、下降中の金型に挟まれそうになった
- ごみ収集車の回転板を清掃中、体が巻き込まれそうになった
- クレーン作業中、開始のタイミングが合わず、手をはさみかけた
- 除雪機が後退し続け、転倒した作業者が轢かれそうになった
- ボール盤作業中、手袋が巻き込まれそうになった
出典:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例 はさまれ・巻き込まれ」
このような事例では、「機械の停止確認が不十分だった」「防護措置がされていなかった」「不用意に手や身体を近づけてしまった」といった共通点があります。防止のためには、作業前に必ず機械の停止・遮断を確認し、可動部にはカバーやガードを設置するなどの物理的対策を施しましょう。
4.ヒヤリハットを労災事故防止につなげる方法
ヒヤリハットは、放置すれば重大事故につながる可能性のある重要な兆候です。ヒヤリハットが発生した時点で正しく情報を共有し、職場全体で安全意識を高めることが事故防止につながります。
ここでは、ヒヤリハットを労災予防に活用するための具体的な方法を3つ紹介します。
4-1.ヒヤリハット情報を共有する
ヒヤリハットを防ぐには、まず「報告する」文化を根づかせることが大切です。現場で感じた違和感や危険は、他の誰かにとっても潜在的なリスクとなり得ます。ヒヤリハットが発生した際は、報告書を提出する仕組みを設け、名前の記入は任意とするなど、気軽に報告できる環境を整えましょう。
また、集めた報告は管理者だけでなく全社員が閲覧できるよう、社内掲示板やメールなどで広く共有することも重要です。共有された情報をもとに、社員同士が事例を議論する機会を設ければ、安全意識の底上げにもつながります。
4-2.危険予知訓練(KYT)を行う
ヒヤリハットを未然に防ぐ手段の1つが「危険予知訓練(KYT)」です。KYTでは、実際の現場に即した状況をもとに、どこにどのような危険が潜んでいるかをメンバーで話し合い、予測と対策を可視化します。これにより、普段は見過ごされがちなリスクに気づく力が養われ、日常的な注意力が高まります。
特に、イレギュラーな作業や新人・異動者が多い現場では、KYTの実施が効果的です。定期的な訓練を通じて危険感受性を高め、職場全体の安全レベルを底上げしましょう。
4-3.安全研修を実施する
安全意識の向上には、ヒヤリハットの重要性やハインリッヒの法則の理解を深める安全研修が欠かせません。特に、新入社員やパート・アルバイトなど、安全活動に不慣れな人には、基本から学べる研修を実施することが効果的です。
また、社内で発生したヒヤリハット事例を用いたケーススタディを取り入れれば、実感を伴った学びが得られます。さらに、安全大会や表彰制度を設けることで、日頃から安全に配慮した行動が評価される風土を築けます。全社員が「自分ごと」として安全を意識できる環境づくりが、事故防止につながります。
まとめ
重大な事故の背景には、見過ごされがちな小さな異変やヒヤリハットが存在します。重大事故防止のためには、事故につながりかねない小さなサインを正しく捉え、共有し、職場全体での安全意識の向上につなげる仕組みが不可欠です。職場全体で「気づき」「学び」「共有」する文化を醸成し、無事故を実現しましょう。