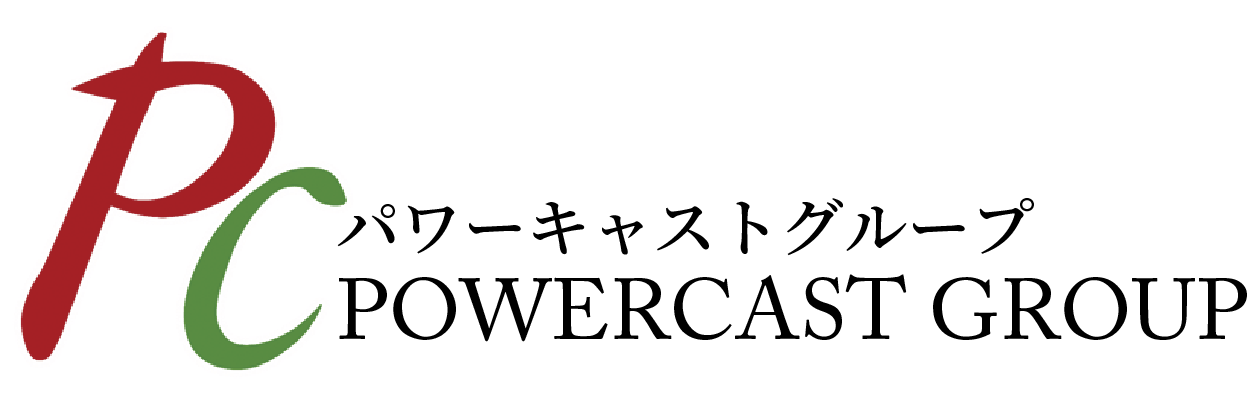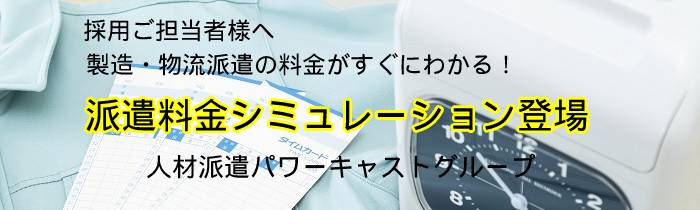2024年10月に社会保険適用拡大!従業員51人以上の企業に必要な対応
2024年10月から、社会保険の適用範囲が広がりました。特に影響が大きいのがパートやアルバイトを多く抱える企業で、「どの従業員が新たに加入対象なのか」「企業の負担が増えるのでは?」という悩みや疑問をお持ちの方も多いでしょう。企業側が対象者の把握や適切な手続きができていない場合、従業員とのトラブルや法令違反に発展しかねません。
当記事では、社会保険の新たな加入対象となる従業員の条件や必要な手続きを詳しく解説します。実際の対応方法や企業にとってのメリットも示しているため、スムーズな企業運営を推進したい方はもちろん、人材の定着や採用力の強化を目指す方も参考にしてください。
目次
1.【2024年10月】社会保険適用拡大のポイント
2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されました。これは、2022年6月に公布された「年金制度改正法」に基づいて実施されたものです。
そもそも社会保険とは、会社に勤める正規社員や一定条件を満たす非正規社員を対象に、病気やケガの備えとして加入が義務付けられている公的保険制度です。広義の社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5種類を指します。このうち健康保険・介護保険・厚生年金保険の3種類は狭義の社会保険に分類されます。雇用保険・労災保険は「労働保険」と総称され、狭義の社会保険とは区別されます。
| 社会保険(広義) | |
|---|---|
| 社会保険(狭義) | 労働保険 |
|
|
ここからは、2024年10月から社会保険適用拡大の対象となる企業や、パート・アルバイトの加入要件について詳しく紹介します。
1-1.社会保険適用拡大の対象となる企業
2024年10月からは、従業員数51人以上の企業が社会保険適用の対象となりました。従業員数は下記の方法でカウントします。すでに社会保険に加入している正社員だけでなく、一部のパート・アルバイトも含めます。
従業員数 = フルタイムで働く従業員 + 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員
なお、従業員数が50人以下の企業は、今回の社会保険適用拡大の対象外です。しかし、企業が任意適用事業所の申請を行い認可を受ければ、一部のパート・アルバイトも社会保険に加入することができます。
1-2.加入対象となるパート・アルバイトの要件
従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの社会保険加入条件は、下記の通りです。
・1週間の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上である
フルタイム労働者の1週間あたりの所定労働時間が40時間の場合、「20時間以上30時間未満」のパート・アルバイトが加入対象となります。なお、これは契約上の所定労働時間を指しており、残業時間は含まれません。
・所定内賃金が月額8.8万円以上である
1か月の基本給と手当の合計額が8.8万円以上のパート・アルバイトが加入対象となります。残業代や賞与、その他手当などは所定内賃金に含まれません。
・2か月を超える雇用の見込みがある
短期間の雇用ではなく、2か月を超える継続的な雇用が見込まれるパート・アルバイトが加入対象となります。
・学生ではない
学生は基本的に社会保険の加入対象外ですが、定時制・通信制の学校に通う方や休学中の方は加入対象となります。
2.社会保険の適用拡大による企業側のメリット
社会保険の適用拡大により、従業員数51人以上100人以下の企業は下記のメリットを享受できるでしょう。
●人材確保・人材定着がしやすくなる
社会保険に加入できる求人を魅力的に思うパート・アルバイト労働者は少なくありません。社会保険の適用によって従業員に安心感を与えられ、優秀な人材を確保できるほか、定着率を高めることにもつながります。
●パート・アルバイトのシフト調整がしやすくなる
パート・アルバイト労働者は、社会保険に加入することによって年収の壁を気にせず働けるため、安定してシフトを組めるようになります。結果として、事業者側もシフト調整がしやすくなるというメリットを得られるでしょう。
●多様な価値観をもつ従業員のモチベーション向上につながる
社会保険は、年金や医療保障をサポートする福利厚生の一環として活用することが可能です。福利厚生が充実することで、「長く働きたい」「子育てや介護をしながら働きたい」などのさまざまなニーズを持つ従業員の満足度が高まり、働く意欲も向上するでしょう。
3.社会保険適用拡大の対応に必要な手続き
社会保険の対象企業は、適用拡大に対応するための社内手続きを進める必要があります。ここからは、社会保険適用拡大の対応に必要となる加入手続きを、順を追って分かりやすく説明します。
3-1.STEP1:加入対象者を把握する
まずは、勤務時間と賃金から社会保険の加入対象となる従業員を把握しましょう。契約上の勤務時間や賃金を確認し、所定労働時間がフルタイムの4分3以上なのか、1か月の賃金が月額8.8万円以上なのかをチェックします。雇用期間や、学生の場合は課程の種類なども確認が必要です。
対象となる従業員を把握した後は、既存の給与計算システムやExcelなどの表計算ツールを活用して社会保険加入の対象となる従業員を一覧化する形で管理すれば、対象者の漏れを防止できるでしょう。その際、従業員に対する説明の進捗状況なども整理しておくと、情報の管理が効率的になります。
3-2.STEP2:自社の対応方針を検討する
社会保険の適用対象者を把握したら、次に自社が対応すべき方針を決定します。パート・アルバイトが新たに社会保険に加入することで、事業主が負担する社会保険料は変わります。そのため、まずは人件費を試算し、社会保険加入後の企業によるコスト負担を見積もりましょう。負担すべき社会保険料の試算は、厚生労働省が運営する「社会保険適用拡大特設サイト」内の「社会保険料かんたんシミュレーター」から簡単に行えます。
試算結果をもとに、自社の対応方針を検討します。たとえば、社会保険加入後に負担が増える場合、その調整策として「勤務時間の見直しや新たな雇用形態の導入」を検討することで、企業の経営効率を維持しつつ従業員の労働環境も最適化できます。今後の方針を策定したら、経営陣や幹部からの承認を得ましょう。承認を得た後は、現場責任者に具体的な方針内容を説明し、実行に移す準備を整えます。
3-3.STEP3:社内に通知する
加入対象者や社内の対応方針が明確になったら、新たに加入対象となったパートやアルバイトなどの短時間労働者に通知します。社内通知は、従業員が頻繁に利用する社内のイントラネットシステムや、業務連絡で日常的に使用するコミュニケーションツールなどで行うと効果的です。
しかし、文章だけでは理解が難しいケースもあります。社会保険の加入に疑問や不安を抱く従業員もいるため、直接コミュニケーションを取って不安を解消することも大切です。コミュニケーションツールを活用した周知だけでなく、個別面談などほかの周知方法と組み合わせて実施することで、より高い周知効果が期待できるでしょう。
3-4.STEP4:必要に応じて従業員とコミュニケーションを取る
社会保険適用拡大に関する通知を受けて、社会保険の加入に疑問や不安の声が上がった場合は、個別面談や説明会を通して従業員とコミュニケーションを取るようにしましょう。特に説明会は、一度に多くの従業員とコミュニケーションを取れる方法です。企業の人事・労務管理者が実施するケースのほか、外部の社会保険労務士を講師として招くケースもあります。
しかし、パート・アルバイトなどの短時間労働者は勤務時間中の説明会参加が難しいこともあります。全員が参加できるよう、オンラインと対面両方の形式で開催したり、対面で実施した説明会の様子を後日動画で配信したりするなど、柔軟に対応することが重要です。
3-5.STEP5:被保険者資格取得届を作成・提出する
最後に、社会保険に加入するための手続きを行います。特定適用事業所に該当する企業で社会保険の適用を受けるパート・アルバイトがいる場合、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出する必要があります。被保険者資格取得届の届出は、日本年金機構サイト内の「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」からオンラインで24時間いつでも申請可能です。
電子申請を利用する場合は、日本年金機構の電子申請サイトから手続きを行います。紙媒体で提出する場合は、日本年金機構サイト内の「従業員を採用したとき」から必要な届出用紙をダウンロードし、必要事項を記入した後で郵送しましょう。
まとめ
2024年10月の社会保険適用拡大で重要なのは、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者の一部が新たに加入対象となったことです。特に、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上、月額賃金が8.8万円以上、2か月以上継続して雇用されるパートやアルバイトは社会保険への加入義務が発生します。企業側は対象者を明確に把握し、加入手続きを進めましょう。
社会保険の適用は今後も拡大する可能性があります。小規模な企業でも社会保険加入義務の範囲が広がることを見据え、必要な準備を整えておきましょう。